──「コピーレフト」や「冗長性」から見る言語文化の深層──
はじめに
IT業界の専門用語には、まるで詩やジョークのように、ウィットや思想が込められているものが少なくありません。
たとえば、「コピーレフト」や「ソーシャルエンジニアリング」などは、単なる技術用語にとどまらず、言葉自体が風刺や哲学を帯びた象徴として機能しています。
今回は、そんなIT用語のなかでも、**「言葉遊び」や「定義の変容」**に着目して、IT技術者の思考や文化を読み解いていきます。
1. 遊び心に満ちたIT用語
● コピーレフト(Copyleft)
著作権(copyright)に対する逆説的な表現。
- 由来:「right(権利・右)」に対して「left(左・残された)」を掛けた言葉遊び。
- 思想:知識やコードは自由に共有されるべき、というオープンソースの精神。
ここには、自由主義 vs 所有権の構造的な問いが埋め込まれており、単なる洒落以上の意味を持っています。
● ソーシャルエンジニアリング(Social Engineering)
人間心理の脆弱性を突く攻撃手法。
- 本来の意味:社会制度を設計する学問(社会工学)
- 転用の妙味:制度ではなく「人間」を設計・操作するというブラックユーモア。
「人は最弱のリンクである」という、皮肉を込めた警句が込められているようです。
● スラッシュドット効果(Slashdot Effect)
- 意味:人気技術サイトにリンクされて、アクセスが殺到しサーバが落ちる現象。
- 元ネタ:「http://slashdot.org」というURL自体が、読みづらさを逆手に取ったジョーク。
この用語には、インターネット文化の草の根的なユーモアが根づいています。
2. IT業界独自の定義・再解釈
● 一意に決まる
- 一般語では「明確に決まっている」程度の意味。
- IT語では、入力に対して出力が「関数的に決定される」ことを意味します。
→ たとえば、ハッシュ値は同じ入力なら常に同じ出力になる=一意に決まる。
数学的な厳密性が背景にあります。
● 冗長性(Redundancy)
- 日常語:「ムダ」「不要な重複」
- IT語:「障害に備えた意図的なバックアップ設計」
→ RAIDやクラスタ構成など、「万が一」に備えた信頼性設計を意味します。
ここでは、「余計」が「必要」に変わっているのです。
● 落ちる(クラッシュ)
- IT語での「落ちる」は、「プロセスが異常終了する」ことを意味する比喩。
- 実体がないはずのプログラムに対して、「物が落ちる」という具体的な感覚を与える表現。
抽象世界を扱う技術者が、身体的な言語感覚でそれを補っている一例です。
まとめ
IT業界の用語には、単なる「定義」ではなく、思想・皮肉・詩的なニュアンスが込められています。
言葉を通して、エンジニアたちは自分たちの世界を語り、笑い、問いを立ててきたのです。
もしあなたがITを学ぶ立場にあるなら、こうした言葉に宿る“文化”にも耳を澄ませてみてください。
技術を超えて、ことばの深みを味わう知的な冒険が待っています。

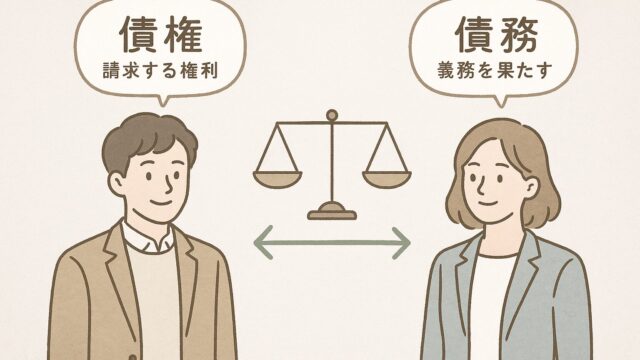

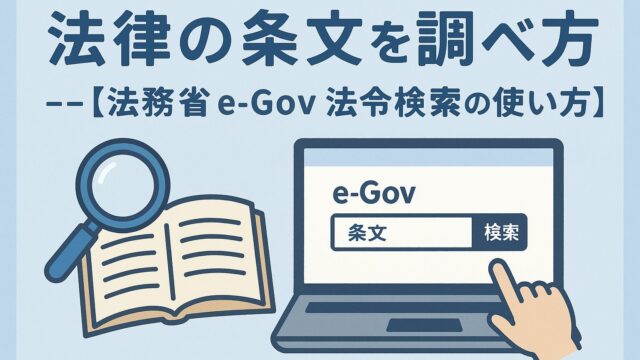
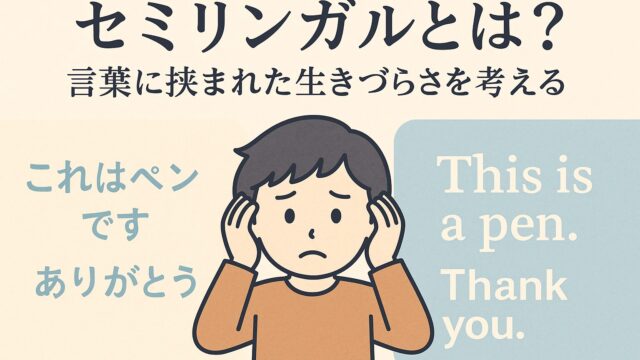

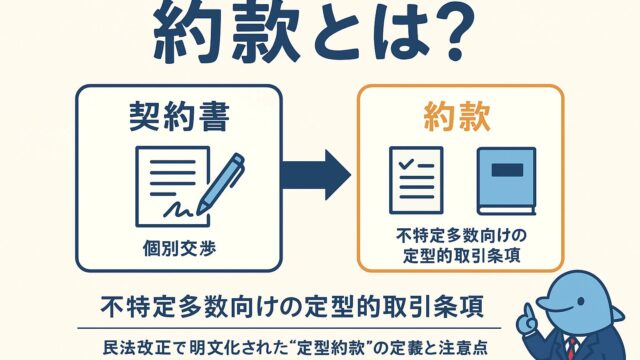

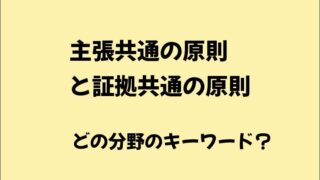
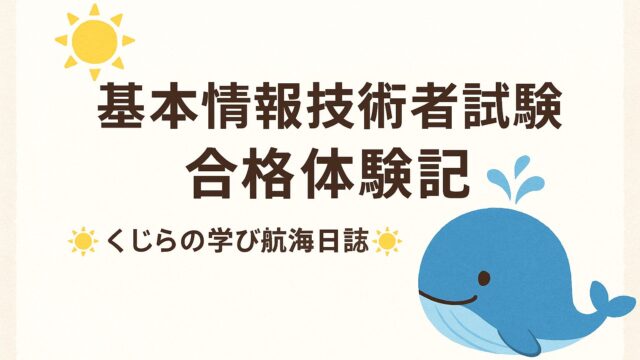



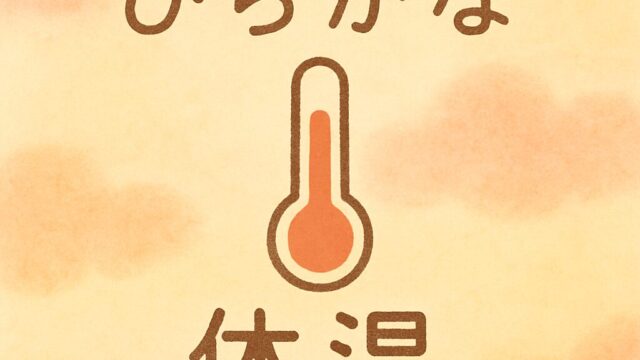
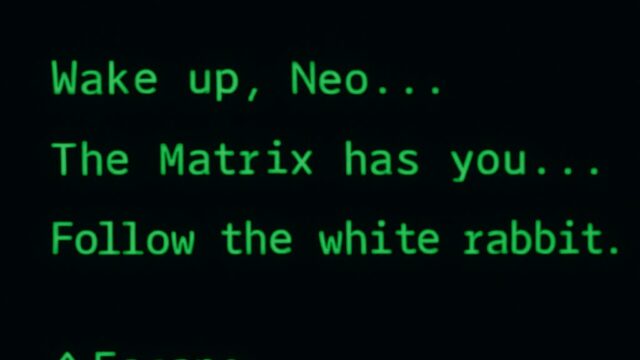
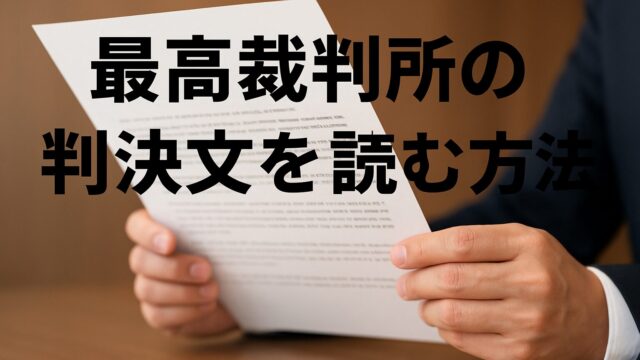
コメント