導入
思考や感情をそのまま外に取り出すとき、言葉の選び方ひとつで、その「体温」が伝わるかどうかが変わる。
特に日本語では、「漢字」と「ひらがな」という二つの表記体系が、伝える温度を左右すると私は考える。
この文章では、このような、日本語の柔軟性について考察したい。
日本語話者としての「幸運」
1つの言葉をとっても、それを「漢字」で書くのか、「ひらがな」で書くのか――その一手で文章の印象ががらりと変わる。
日本語には、そういった微妙な表現の幅がある。
これは煩わしさでもあるが、思考や感情を精密に伝えるうえで、実に豊かな可能性を秘めている。私たちは、日本語を使い、言葉の「温度」を選び取ることができるのだ。
ひらがなの金属質な「熱伝導率」
ひらがなには、不思議と「生のままの感情」を伝える力があると感じる。
それはまるで、熱伝導率の高い金属のように、こちらの熱をそのまま相手に伝える導管のようだと感じる。
硬く冷たいのではなく、むしろ熱しやすく、冷めやすく、軽やかに流れる媒体、そういった感触。
漢字がまとった「生活の色」
一方で、漢字は人それぞれに「歴史」や「記憶」が染み込んでいる。
ときに、ある漢字を見て心がざわつくことがある。それは、その言葉に自分だけの体験が焼きついているからかもしれない。
漢字は意味を背負いすぎてしまう――そういう側面もあると感じる。
言葉で届けるということ:ストーリーとコピーの違い
ストーリー作品であれば、読者の心をゆっくりと温めながら、その受け止め方を誘導できる。
しかし、(キャッチ)コピーやタイトルのような瞬発力のある表現では、それができない。限られた言葉のなかで、相手の「体温」と瞬時に共鳴しなければならない。
その難しさと面白さは、いつも私を惹きつけてやまない。
ちなみに、私の最も敬愛するコピーライターは秋山晶氏である。またいつかその魅力について語りたい。
結び
言葉には体温がある。どんな表記で、どんな語感で届けるかによって、相手に伝わる「熱」は変わる。私はこれからも、ひらがなと漢字のあいだで揺れて、自分だけの温度で言葉を編んでいきたいと思う。

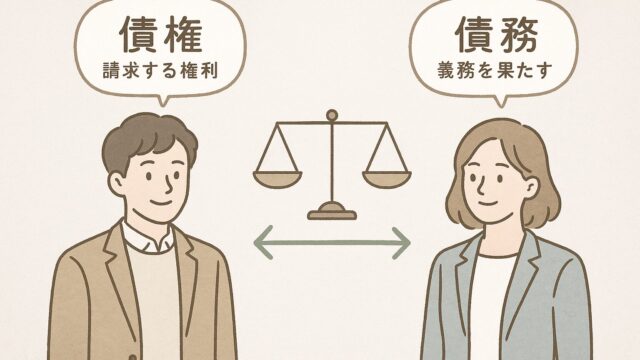
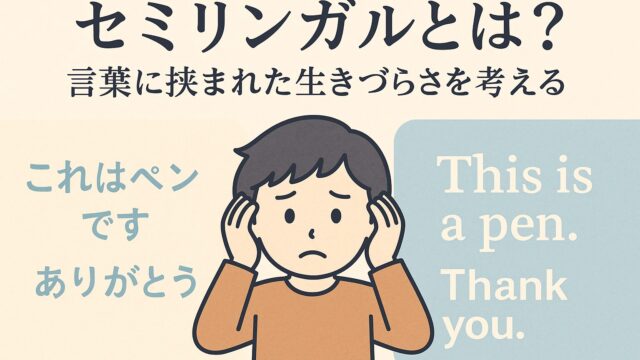

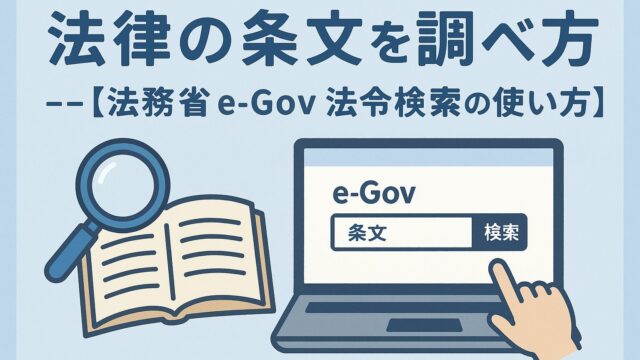

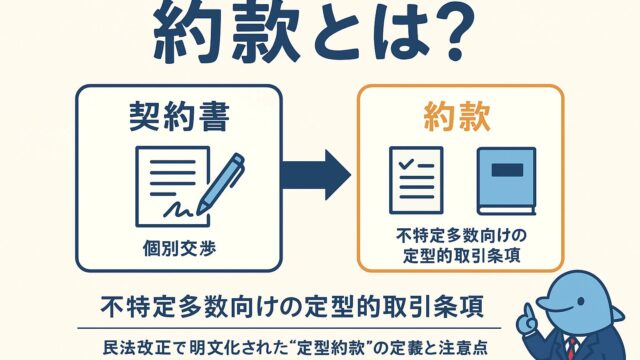

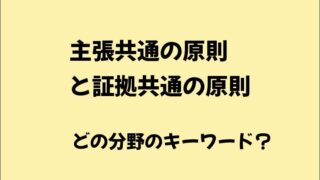


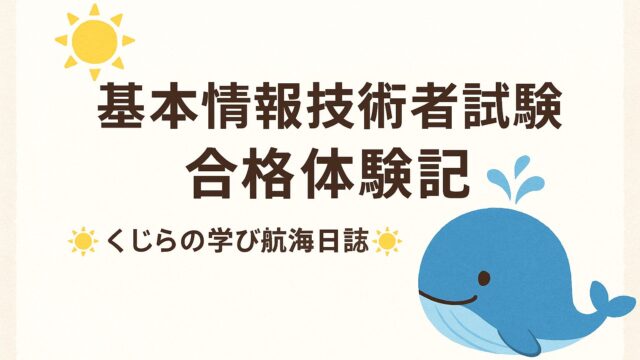


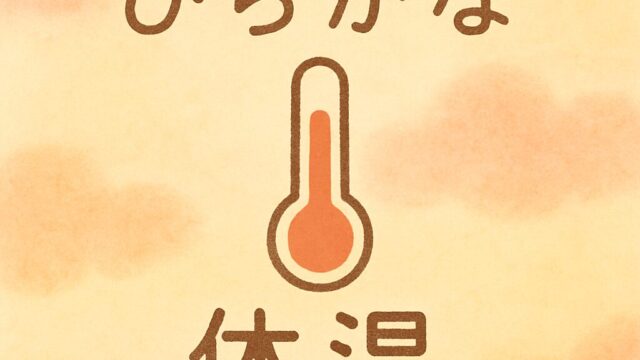
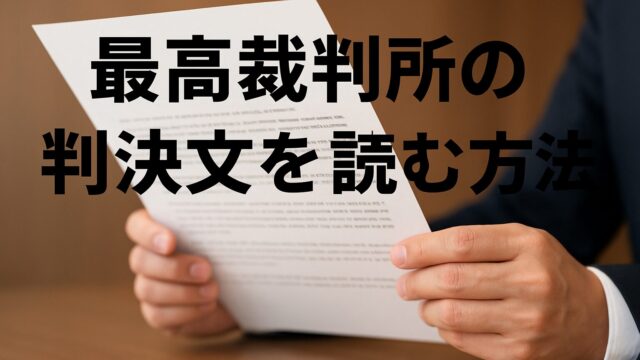
コメント