──慢心は“実力”ではなく“自己設定”から生まれる
はじめに
漢字でも、英単語でも、専門知識でも――
「もうこれで十分」と思った瞬間から、学びの在り方は変わります。
どこかで“終点”を設定してしまうと、そのあとに出会う未知の情報は、自分を脅かすものになってしまう。
驚き、恥じ、そして「こんなはずではなかった」と、穴を埋めるように知識を追いかけることになる。
これは、知識が足りないからではありません。
「足りないと思わなくなった」から、心が乱れるのです。
必要十分の漢字を覚えたはずなのに
日常でふと出会う、読み方の分からない漢字。
かつてなら「知らなかった」で済んだはずなのに、
「もう十分知っている」と自負していた後では、なぜか居心地が悪くなる。
驚き、恥ずかしさ、不安……
自分が思っていた“完成状態”が、たやすく崩れてしまうからです。
慢心は「できるようになったから」ではない
私たちはつい、こう考えがちです。
「ある程度できるようになった」=「慢心が生まれる」
けれど実際には、慢心の原因は“習得度”そのものではありません。
慢心は、自分自身が引いた「ここまででいい」というゴール設定によって生まれます。
つまり──
「終わった」と思った瞬間に、学びが止まるのです。
知識の穴に出会ったとき、人は2つに分かれる
学びの途中で新しい知識に出会ったとき、人は次のどちらかに分かれます。
- 「えっ、知らなかった!もっと知りたい」と、前向きに学び直す人
- 「今さらこんなこと知らなかったなんて…」と、恥じて目をそらす人
この違いを生むのは、ゴール設定の有無です。
学びを「終わりのあるもの」と思えば、未知との出会いはストレスになります。
逆に「学びに終わりはない」と思えば、未知との出会いは喜びになります。
専門分野でも、同じことが起きている
これは漢字や一般教養だけの話ではありません。
たとえば──
- 法律の専門家が、自分の専門外の条文を知らずに戸惑う
- エンジニアが、次世代の技術に触れておらず不安になる
これも、どこかで「もうこの分野ではやっていける」と思った油断の裏返しです。
自分で決めた「終点」が、学びの感度を鈍らせてしまうのです。
結論:「学びの終わり」は心の中にしかない
自分で「もう大丈夫」と思った瞬間から、学びは止まる。
だがその「大丈夫」は、どこまでも主観的で、あてにならない。
慢心とは、実力が十分になったからではなく、
「これ以上やらなくていい」と決めてしまった心の態度から生まれます。
だからこそ、ゴールは常に動的であるべきです。
「ここまで来た」ではなく、
「まだこれがあるかもしれない」
という視点を持ち続けましょう。
そうすれば、未知の知識に出会ったとき、恥ではなく感謝が生まれます。
あとがき
この文章は、ある人のひとことから着想を得て書きました。
漢字一つであっても、人生の深層に気づきをくれることがあります。
自分にとっての「もう十分」は、本当に十分なのか。
そう問い直す時間もまた、学びなのだと思います。
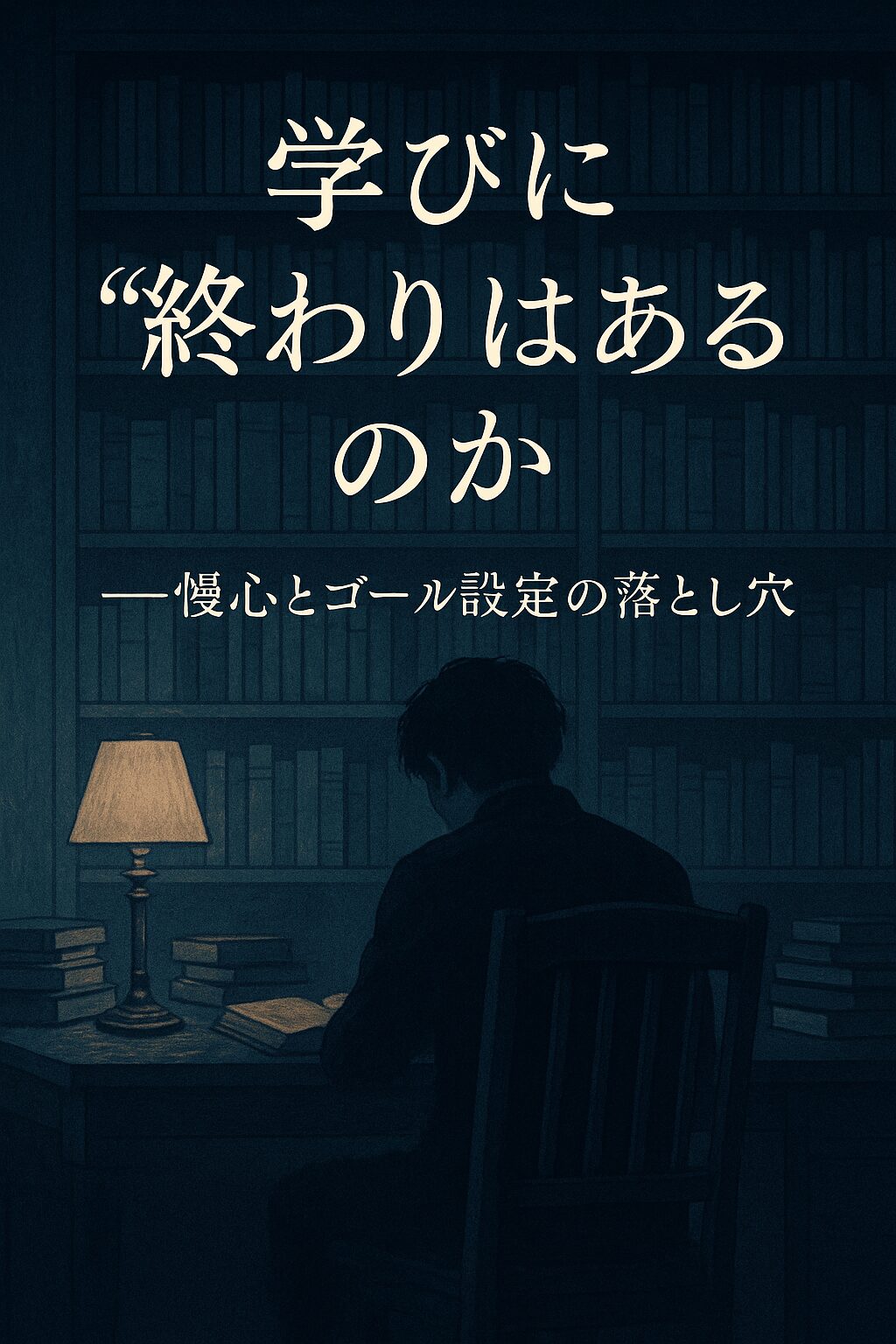
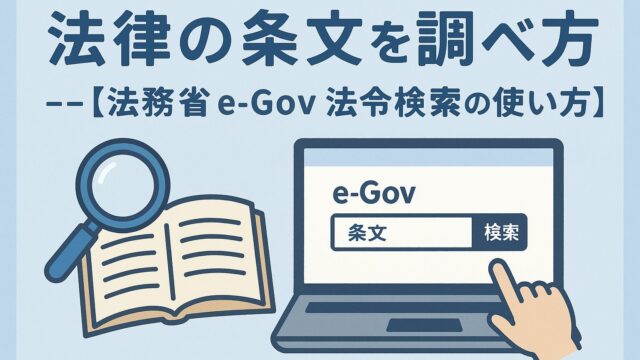
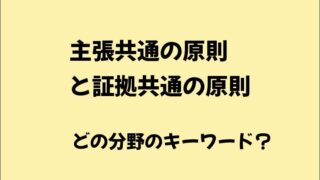

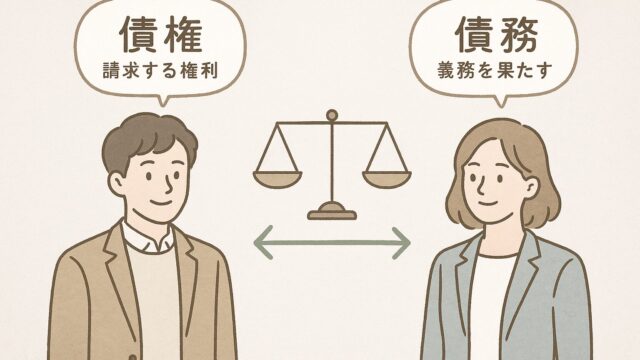
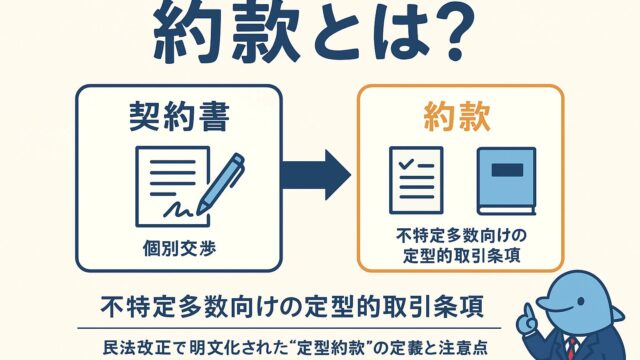



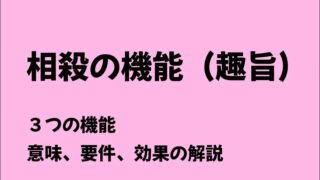
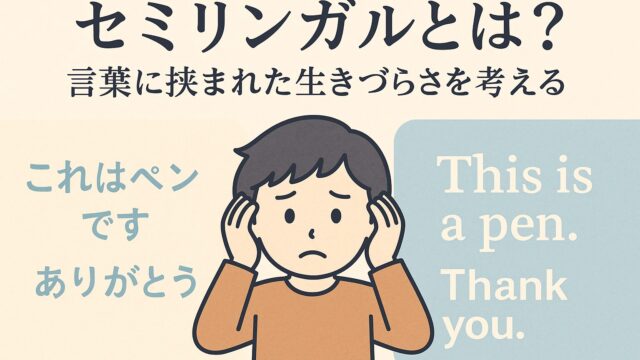

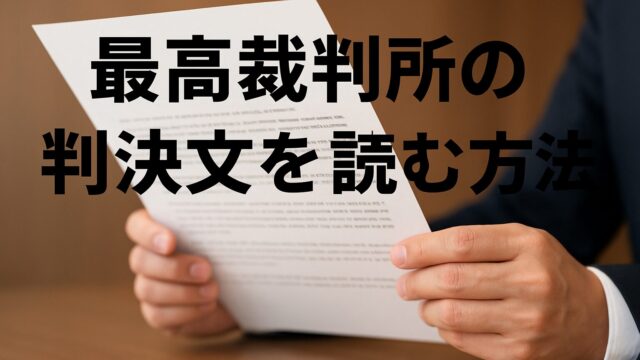
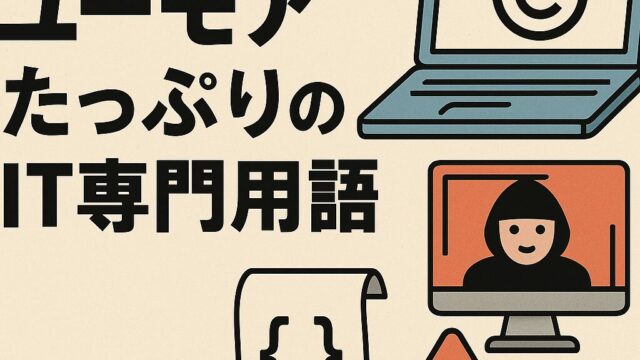

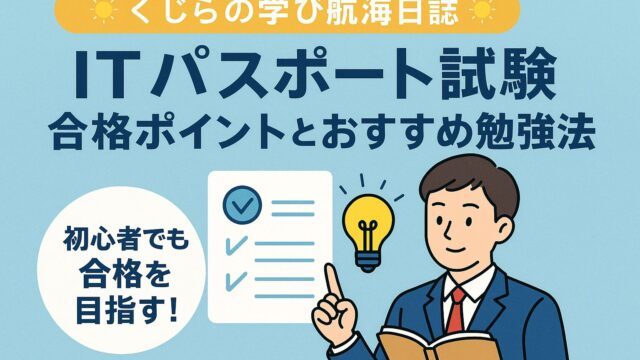
コメント