はじめに
ある事柄が可視化されることは、多くの場合において前向きな変化として歓迎されます。
これまで見過ごされてきた問題に光が当たり、社会の認識が変化し、制度や言説が整っていくことは、当事者にとって大きな意味を持つものだと思います。
しかし最近、その「可視化」が進むとき、同時に生まれてしまう影の存在について考える機会がありました。
光が強くなればなるほど、その光の輪郭の外側には、より濃く深い影が落ちるのではないか──そのような懸念を抱く場面が増えているように感じています。
可視化が生む希望と、見えにくくなるもの
何かが社会に「見える」ようになることは、それまで声が届かなかった人々にとって大きな一歩となります。
LGBTQ+、ジェンダー、障害、民族性といった領域では、社会的認知が広がることで、ようやく語られるようになった経験や存在が多くあります。
ただし、その語りの中に「代表的なイメージ」や「典型的な構図」が生まれると、それに当てはまらない声がかえって見えにくくなるという事態が生じます。
たとえば、LGBTQ+においてゲイ男性の語りが広がる一方で、トランスジェンダーやバイセクシュアル、ノンバイナリーの経験が十分に届かないことがあります。
また、「女性の権利」が論じられる際に、白人中産階級女性の視点が無意識のうちに基準とされ、異なる立場の女性たちがその周縁へと押しやられてしまう現象も見受けられます。
こうした状況は、語られることによって一部が「代表」となり、それ以外が不可視化される、という皮肉な逆転を示しているように思われます。
インターセクショナリティという視点へ
このような複雑な構造を丁寧に捉えるために、近年「インターセクショナリティ(交差性)」という概念が重要な役割を果たしています。
インターセクショナリティとは、性別・人種・階級・障害・性的指向といった複数の社会的属性が、単独でではなく交差することによって人々の経験を形づくっているという視点です。
たとえば、女性であることと、移民であること。
障害をもっていることと、貧困状態にあること。
それぞれの属性が絡み合うことで、単なる「女性」や「障害者」としては捉えきれない複雑な現実が生まれます。
「光が強くなるほど、影も濃くなる」という感覚は、まさにこのインターセクショナリティの問題意識と通じる部分があるように思います。
何かが照らされたとき、それによって見えにくくなった交差点にこそ、注目する必要がある。
そうした視点が、今の時代にいっそう求められているのではないでしょうか。
思考の背景にある読書体験
このような考えを深めるうえで、藤高和輝氏の『バトラー入門』を読んだことが大きな刺激となりました。
同書では、ジュディス・バトラーの理論、とりわけ「カテゴリーに収まらないもの」「語られなさの中にある抵抗」に関する議論が、平易な言葉で丁寧に解説されています。
読んでいく中で、「可視化されること自体が排除を生む場合がある」という逆説的な構造や、「語られない存在の周縁に目を向けること」の倫理的意義について考えるようになりました。
それが、先述の「光と影」という比喩とも自然につながっていったのだと思います。
おわりに──見えるものと、見えないもののあいだで
何かが見えるようになることは、それだけで希望であり、社会が変化していく兆しでもあります。
ただその一方で、照らされた光のすぐそばに落ちてしまう濃い影にも、同時に注意を向ける必要があるのではないかと感じております。
どのように語るか、どのように分類するか。
その営みの中に、知らず知らずのうちに排除や固定化が含まれていないか。
そうした問いを、自分の中に持ち続けながら、今後も物事を見つめていきたいと思っております。

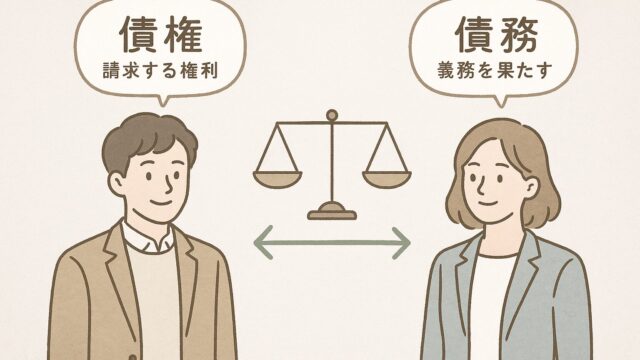




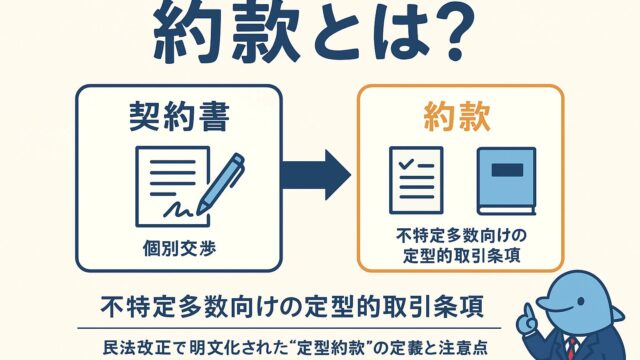

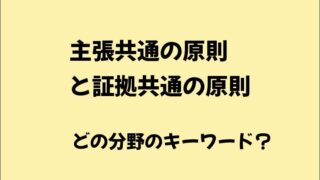






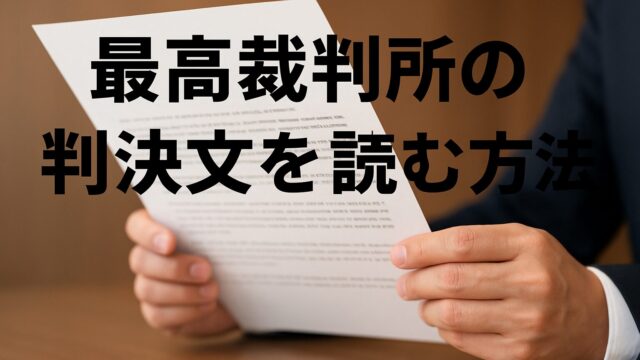
コメント